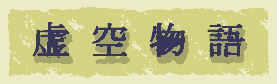
此処には妄想者多田要太による物語を所収しています。
多 田 要 太
第9話 ときのおわり
今夜で世界が終わるというので会社では通常の仕事はせず、裏庭に大きな穴を掘って時計やタイムレコーダやカレンダや作業日報などを放り込んで埋めたりして、まだ日のあるうちに退社した。
自転車で家路をたどりながらふと鼻歌をうたった。『なぜ太陽は輝き続け波は岸に打ち寄せるのか?世界がおわってしまったというのに』という内容の古い歌だ。この歌の邦題が「世界の果てまで」なんていうトンチンカンなことになっているというのは高校の英語の授業でオールドミスの教師が教えてくれたことだった。肝心の英文法はきれいに忘れてしまったのに、こんなどうでもいいことだけはよく覚えている。
世界がおわると判ったのは今から半年くらい前のことだ。ノーベル賞を貰った物理学の先生が、テレビで言ったのだ。事業仕分けに抵抗して勝ち取ったスーパーコンピュータで計算し、膨張する宇宙の外側を解き明かす計算を試みたところ、まもなく『時間』が終わるという解を得たというのだ。
この世界は彗星や隕石の衝突でもなく、未知の宇宙細菌の為でもなく、太陽のスーパーノヴァ化でもなく、核戦争でもなく、細菌兵器でもなく、宇宙人の襲来でも、キングギドラの襲来でもなく、時間が終わることによって消滅するというのだ。
物質や生命が滅んでも時間だけは流れ続けているものだと思っていたが、そうではなかった。二者は不可分なのだ。物質にも生命にも固有の時間があり、物や生物の消滅とともにその時間も終わる。あるいは時間が終わったので物質が消滅すると考えることもできるわけだ。
この世界はどうやら巨大な砂時計のようなものらしい。僕らが『宇宙』と呼んでいる空間はその砂時計の砂の一粒に過ぎず、僕らにとって永遠に続くと思われた『時間』も、その砂時計の砂の一粒が上から下に落ちる間のことに過ぎないということらしい。世界が消滅する瞬間僕らは苦痛を感じるのだろうかと心配したが、ノーベル賞の先生によれば時間がなければ痛みも苦しみも存在しえない。我々は最後の瞬間にすら気付くことなく時とともに消滅するだけなのだそうだ。
そのテレビを見終わった後、そういえば、科学は科学者が事業仕分けに抵抗して勝ち取ったスーパーコンピュータによってようやく『時の終わり』を発見したけれど、音楽は二十世紀の中ごろにそのことに気付いていたのだと思い至った。オリビエ・メシアンが千九百四十年に作曲した『世の終わりのための四重奏曲』の原題は『QUATOUR
POUR LA FIN DU TEMPS』。まさに時の終わりのための曲であった。
メシアンによれば時が終わり永遠が始まるらしいのだが、有限なる生命に過ぎない僕らは、永遠の何たるかを知ることが出来ない。とはいえ、僕らは何となく感じてはいたのだ。ここ数年来の何とも言えない閉塞感。個人的に鬱周期に入ったからかと思っていたが、世間一般何かヘンな感じがあった景気が良くならないのも、投げやりな事件が多いのも、みんな本能的に何か感じていたのではなかったか。それが証拠に、科学者の発表を聞いても、パニックや暴動が起きるわけでもなく、世界的に、なんだやっぱりそうだったかといったような落ち着いた感想が大勢を占めた。
時の終わりのまであと二週間となったころから世界は本当に静かになった。ほとんどの会社は生産を止めてしまった。対立していた人や国が争うことを止め、お金に余裕のある人たちは最後の時を思い思いの場所で過ごす為に旅立っていった。お金のない人や出不精のひとは家で静かに過ごすことを選んだ。テレビでは連日『地球最後の日』だの『世界大戦争』だの『復活の日』だのといった古い映画ばかり放送していた。
そして、いよいよ今夜、時が終わるという日がきてしまったわけだ。会社帰りの道すがらいつも持ち歩いているオリンパスXAで静かな街を写真に撮った。いつもフイルムを現像してもらっていたワン・アワーフォトショップも、もう営業をしていないし、仮に現像したところでその写真をこの先だれも見ることはできないのだとわかってはいるのだが、目の前に心引かれる風景があって、手の中にフイルムの入ったカメラがあれば、写真を撮らずにはいられないのだった。
西の空が夕焼けに染まり上空は濃紺に暮れ始めた。家路をたどる僕の頭の中で高田渡が『私の青空』を歌った。
虚空物語8を読む
虚空物語10を読む
目次に戻る