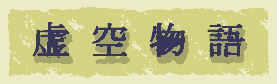
此処には妄想者多田要太による物語を所収しています。
多 田 要 太
第5話 此処ではない何処かへの旅
少年は信号所で停車してゐる気動車の窓から所在無げに外を眺めて居りました。列車はもう二十分も、急行待ちのために此処に停車して居りました。
その日曜日、彼は早くから寝床を抜け出し、自転車で隣町にある国鉄の駅から南へ向かふ列車に乗り込んだのでした。何処へ行かうといふ当ても有りませんでした。只、此処ではない何処かに身を置きたいと思つたのでした。さて暫くの後に急行列車が隣の線路を駆け抜けざまに信号所にタブレツトを渡し、漸く少年を乗せた列車は走り出したのです。
少年は高等學校の二年生でしたが、謳歌すべき青春が何処にあるのか見つけられずに居りました。彼の心には常に、外界と自己との間にある言いやうの無い齟齬が意識せられて居りました。嗚呼、周囲の友人たちの何と溌剌として居る事であらう、何故自分はかくのごとく沈鬱なる毎日を過ごして居るのであらう。彼の疑問に対して學校での學問はその解決法を示しては呉れませんでした。否、彼の未発達な精神のゆへに、学問の根底にある真理に、すなわち彼が求める答えに気付くことができなかつたのです。有態にいへば、彼は、いはゆる愚か者だつたのです。
そんな愚かな少年の心の支えは彼の唯一の趣味である寫眞でした。學校の寫眞部に所属して、毎日課業を終へると部室である地學準備室へ行つては暗室に籠るのでした。赤い安全灯の下で、印画紙に画像が浮かび上がつてくるのを見てゐる時間が其の頃の彼の一番愉しいひと時だつたのです。倶楽部には趣味を同じくする仲間がおり、教場に居る時よりは心も安らぎますが、それでも、他人と接するというのが彼の未熟な神経には重荷であり、其の重荷が日々彼の中に積み重なり、数週間もすると自分では如何ともし難い状況に為つてしまふのでした。さうすると彼の心の中に『此処は自分の居場所では無いのではないか』といふ思いが已み難く浮かび充満してしまふのでした。さうして
さうして少年は日曜日早くから寝床を抜け出し、鞄に寫眞機を入れて出掛けるのでした。写真機は高校に入つたときに親に買つて貰つた旭光学製のペンタツクスKM型一眼レフでした。
高校の寫眞部員たるものは校内で行はれる行事や運動大会等の寫眞を撮つたり、學校生活の一齣を若々しい感性で切り取つて寫眞コンテストに応募して賞を獲得したりするのがその王道と考えられて居りますが、少年の場合どちらも苦手な分野でありました。春の県総体だの高校野球の予選だの運動会だのといつた行事寫眞は腕章巻いてウロウロと撮影はするのですが、彼にとつてはフヰルムを現像する氣すら起こらない被写体ばかりでした。では彼は何が撮りたかつたのでせうか。
彼は日曜毎に自転車で近くの海岸や港や田圃や河原に行つてはボンヤリ佇み、波や船やカモメや稲や草叢やなにかを撮つて居りました。いわゆる『決定的瞬間』と無縁のユルイ寫眞が彼の好みでした。
『決定的瞬間』という呪縛が寫眞には課せられて居りました。例えば運動選手の躍動する肉体の瞬間を切り取つた寫眞には被写体の持つ崇高な精神や筋書きの無いドラマや鍛錬された筋肉の美や爽やかな青春の涙や勝利の雄叫びや明日への希望や全国制覇の野望やらなんやらかんやらが一枚の寫眞の中にぎゆうつと凝縮されていなければならないのでした。さうしてそこに簡潔なタイトルが冠せられていなければなりませんでした。曰く、『躍動』亦は『感動』あるひは『近藤』 。
しかし少年はそんな寫眞が作れないのでした。汗臭い運動寫眞も陰気臭い制服姿のスナツプも彼には遠い彼方にある世界だつたのです。現在只今身を置いている世界が『自分の居るべき世界でないやうな氣がする』それは少年の脆弱な心が彼を取り巻く世界との交渉を避けようとしての言い訳なのでせうか。だつて世界は常に否応無く彼を取り巻いてゐるのですから。
彼にしても、だう足掻いたところで、この世界から逃げ出せないことは解つて居りました。ですから、例え日曜日の朝誰にも告げず汽車に乗つても、そのまま世界の果てまで旅をするやうなことはなく、夕方には家に帰つて夜には明日提出する宿題をやつたりするのです。とりあへず彼は、帰宅するまでの時間、いくつかの小さな町で汽車を降り、町の中や海辺や山際で寫眞を撮りました。誰一人彼のことを知る人がいないという孤独と表裏をなす開放感は彼を少しばかり慰めましたが、勿論どの町も彼が逃げ出したい現実世界と地続きであることに変わりはありませんでした。例えば朔太郎の描く猫町や亂歩の妄想したるパノラマ島は終に彼の眼前に出現することは無かつたのです。
彼はちよつとした氣分転換によつて心地よい疲労感と数本の撮影済みフヰルムを持つて家に帰りました。
さうして少年は、また嫌々ながらも世界に身を沈めて生活を続けたのでした。日々の暮らしに紛れて、旅のフヰルムの殆どは引き伸ばされることもありませんでした。幾星霜かが過ぎ去つて、心弱い愚かな少年は心弱い愚かな中年に成りました。さうして或る日、彼は氣付くのです。彼が求めた『此処ではない何処か』は既に彼の手の中に在つたのです。あの日、撮影した町は、彼のペンタツクスのレンズによつて『現実の町に似てはゐるが、何処でもない、彼の寫眞の中にだけある彼だけの町』に成つていたのです。彼のネガフアイルには彼の『何処か』が詰まってゐるのです。中年に成つても未だに高校生の時と同じやうな寫眞を撮り続けてゐるのは、それこそが彼の希求する世界を現前させる方法だつたからなのです。愚か者はそれに気付かぬまま、寫眞を撮ることによつて、日々『此処ではない何処か』へ旅してゐたのです。
虚空物語4を読む
虚空物語6を読む
目次に戻る