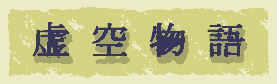
此処には妄想者多田要太による物語を所収しています。
多 田 要 太
目 次
第6話 夢路 その1
第5話 此処ではない何処かへの旅
第4話 あるばむ譚
第3話 ほいとのはなし
第2話 獺祭老人伝
第1話 裸で暮らした我等の先祖は
夢路 その1
その朝大便をしたトイレは道路から石垣で1メートルほど高くなった畑の隅にあって、困ったことに囲いが全く無くて道路を歩く人から丸見えだった。でも、慣れたら全然気にならないト思いながら用を足して、下を見ると便槽のなかにエアガンの瓦斯缶などが落ちているので、汲取屋に怒られるト思い火箸で取って畑の横の廃材置き場に捨てた。汲取屋はここがトイレだと知っているのだろうか。どう見ても只の穴なのだが。
前の晩はムラタ君の家に泊めてもらっていたのでそのまま会社に行こうト思い他の友達たち(大学の写真部の友達だったような気がするがよくわからない)と一緒に表に出たら最近ムラタ君が飼いはじめたという犬が寄ってきたのでそういえば、会社のパートさんにもらったミルクキャンデーがあったト思い鞄を探ると、粒餡の饅頭が出てきた。これは何時から入っていたのだろうト不安になるが、犬に食わせるのだから賞味期限なんて大丈夫、一応臭いをかいで見るが花粉症で鼻が詰まっているのでポーズだけ。でもその茶色の子犬は地面に割り置かれた饅頭を迷惑そうに眺めるだけで食べようとしない。慌てて鞄を探りキャンデーをやるがそれも気に入らないようだ。見ると犬の顔がだんだんと吻が伸びて目玉も飛び出して来そうだったので構うのを止めて早々にその場を辞した。
土塀に囲まれた路地を曲がると四国の田舎の海岸近くの畑の中の道。空は恐怖を覚えるほどの藍色で今日も暑くなりそうだった。海の方角から自転車に乗った女子生徒が二人走ってきた。中学は自転車通学禁止の筈なので何処かの高校生が夏の補習のために登校するのだろう。水を汲み上げて畑に潅水するモーターの音が遠くで聞こえる。昔は無かったでっかいタンクがたくさん建っていて、こりゃマイケルケンナな風景だ夜に撮影しにこようト思った。畑の中の舗装されてない細い道をたどっているうちに曲がり角が判らなくなってしまった。家に帰って自転車で会社に行ったほうが帰りが楽だト思ったのだが、このままでは遅刻してしまう。適当なところで旧国道を渡ったら、見覚えのある製材所が在った。しまった、景色に気をとられて行き過ぎた。ここはもう伊予市だ。こうなったら電車で帰ろうと駅に向かう。黒い犬がしっぽを振って走ってきて足に纏わりつく。さかりがついているのだ。昔は無かった大きなスーパーに迷い込みそうになったりしながらやっと郡中港の駅に着いた。電車は行ってしまった後だった。電話を探して会社に遅刻する旨連絡しなければト思うのだが公衆電話が見当たらない。駅のトイレの脇にピンク色の電話があったので、十円玉を入れようとしたら投入口が溶接で塞がれていた。駅員に教えてもらってやっと電話のありかが判ったが、今度は会社の電話番号を控えた手帳の頁が判らない。そうこうしているうちに始業時間が近づいてくる。ああ、今日は朝礼の日じゃないか。こまったなあト思ったら。
第5話 此処ではない何処かへの旅
少年は信号所で停車してゐる気動車の窓から所在無げに外を眺めて居りました。列車はもう二十分も、急行待ちのために此処に停車して居りました。
その日曜日、彼は早くから寝床を抜け出し、自転車で隣町にある国鉄の駅から南へ向かふ列車に乗り込んだのでした。何処へ行かうといふ当ても有りませんでした。只、此処ではない何処かに身を置きたいと思つたのでした。さて暫くの後に急行列車が隣の線路を駆け抜けざまに信号所にタブレツトを渡し、漸く少年を乗せた列車は走り出したのです。
少年は高等學校の二年生でしたが、謳歌すべき青春が何処にあるのか見つけられずに居りました。彼の心には常に、外界と自己との間にある言いやうの無い齟齬が意識せられて居りました。嗚呼、周囲の友人たちの何と溌剌として居る事であらう、何故自分はかくのごとく沈鬱なる毎日を過ごして居るのであらう。彼の疑問に対して學校での學問はその解決法を示しては呉れませんでした。否、彼の未発達な精神のゆへに、学問の根底にある真理に、すなわち彼が求める答えに気付くことができなかつたのです。有態にいへば、彼は、いはゆる愚か者だつたのです。
そんな愚かな少年の心の支えは彼の唯一の趣味である寫眞でした。學校の寫眞部に所属して、毎日課業を終へると部室である地學準備室へ行つては暗室に籠るのでした。赤い安全灯の下で、印画紙に画像が浮かび上がつてくるのを見てゐる時間が其の頃の彼の一番愉しいひと時だつたのです。倶楽部には趣味を同じくする仲間がおり、教場に居る時よりは心も安らぎますが、それでも、他人と接するというのが彼の未熟な神経には重荷であり、其の重荷が日々彼の中に積み重なり、数週間もすると自分では如何ともし難い状況に為つてしまふのでした。さうすると彼の心の中に『此処は自分の居場所では無いのではないか』といふ思いが已み難く浮かび充満してしまふのでした。さうして
さうして少年は日曜日早くから寝床を抜け出し、鞄に寫眞機を入れて出掛けるのでした。写真機は高校に入つたときに親に買つて貰つた旭光学製のペンタツクスKM型一眼レフでした。
高校の寫眞部員たるものは校内で行はれる行事や運動大会等の寫眞を撮つたり、學校生活の一齣を若々しい感性で切り取つて寫眞コンテストに応募して賞を獲得したりするのがその王道と考えられて居りますが、少年の場合どちらも苦手な分野でありました。春の県総体だの高校野球の予選だの運動会だのといつた行事寫眞は腕章巻いてウロウロと撮影はするのですが、彼にとつてはフヰルムを現像する氣すら起こらない被写体ばかりでした。では彼は何が撮りたかつたのでせうか。
彼は日曜毎に自転車で近くの海岸や港や田圃や河原に行つてはボンヤリ佇み、波や船やカモメや稲や草叢やなにかを撮つて居りました。いわゆる『決定的瞬間』と無縁のユルイ寫眞が彼の好みでした。
『決定的瞬間』という呪縛が寫眞には課せられて居りました。例えば運動選手の躍動する肉体の瞬間を切り取つた寫眞には被写体の持つ崇高な精神や筋書きの無いドラマや鍛錬された筋肉の美や爽やかな青春の涙や勝利の雄叫びや明日への希望や全国制覇の野望やらなんやらかんやらが一枚の寫眞の中にぎゆうつと凝縮されていなければならないのでした。さうしてそこに簡潔なタイトルが冠せられていなければなりませんでした。曰く、『躍動』亦は『感動』あるひは『近藤』
。しかし少年はそんな寫眞が作れないのでした。汗臭い運動寫眞も陰気臭い制服姿のスナツプも彼には遠い彼方にある世界だつたのです。現在只今身を置いている世界が『自分の居るべき世界でないやうな氣がする』それは少年の脆弱な心が彼を取り巻く世界との交渉を避けようとしての言い訳なのでせうか。だつて世界は常に否応無く彼を取り巻いてゐるのですから。
彼にしても、だう足掻いたところで、この世界から逃げ出せないことは解つて居りました。ですから、例え日曜日の朝誰にも告げず汽車に乗つても、そのまま世界の果てまで旅をするやうなことはなく、夕方には家に帰つて夜には明日提出する宿題をやつたりするのです。とりあへず彼は、帰宅するまでの時間、いくつかの小さな町で汽車を降り、町の中や海辺や山際で寫眞を撮りました。誰一人彼のことを知る人がいないという孤独と表裏をなす開放感は彼を少しばかり慰めましたが、勿論どの町も彼が逃げ出したい現実世界と地続きであることに変わりはありませんでした。例えば朔太郎の描く猫町や亂歩の妄想したるパノラマ島は終に彼の眼前に出現することは無かつたのです。 彼はちよつとした氣分転換によつて心地よい疲労感と数本の撮影済みフヰルムを持つて家に帰りました。
さうして少年は、また嫌々ながらも世界に身を沈めて生活を続けたのでした。日々の暮らしに紛れて、旅のフヰルムの殆どは引き伸ばされることもありませんでした。幾星霜かが過ぎ去つて、心弱い愚かな少年は心弱い愚かな中年に成りました。さうして或る日、彼は氣付くのです。彼が求めた『此処ではない何処か』は既に彼の手の中に在つたのです。あの日、撮影した町は、彼のペンタツクスのレンズによつて『現実の町に似てはゐるが、何処でもない、彼の寫眞の中にだけある彼だけの町』に成つていたのです。彼のネガフアイルには彼の『何処か』が詰まってゐるのです。中年に成つても未だに高校生の時と同じやうな寫眞を撮り続けてゐるのは、それこそが彼の希求する世界を現前させる方法だつたからなのです。愚か者はそれに気付かぬまま、寫眞を撮ることによつて、日々『此処ではない何処か』へ旅してゐたのです。
第4話 あるばむ譚
てすさびで作った針穴カメラを持って、公園へ試し撮りに行った。これといって目を引く景色も無いので、適当な場所に三脚を据えていると、近くのベンチに座っていた益田喜頓に似た老人に話し掛けられた。
「オヤ、それは針穴寫眞機でせう。写りは如何ですか」
私が、今日が写し初めなので、性能は判りませんと云うと、老人は私がカメラを向けている風景を見て、怪訝そうな表情を浮かべた。
「此処にははさほど面白い被寫体があるとも思へませんが、折角御作りになつた寫眞機に初めて見せてやるものは、もつと貴方の大切なものを選ぶべきではありますまいか」
こういう場所でカメラを持っていると、カメラマニアのおやじどもににいろいろ質問されたり、薀蓄を聞かされたりして辟易することが多いのだが、この老人のような意見は初めて聞いた。
「これは失礼、見ず知らずのお方に、差し出がましいことを云ひました」
私が手を止めて彼を見たものだから、老人はこう云って謝った。
「イエ、尤もな御意見だと思い感服しておったのです。愛機のシャッターを初めて押すというのに私は今まで、何も考えておりませんでした。それにしても、いざ自分の一番大切なものは何かと考えると、案外難しいですね」
私が云うと老人は一寸微笑んで云った
「さうですね、私の場合は・・・さうだ、もし宜しければ私の寫眞を見にいらつしやい。ナニすぐ近所に住んで居るのですよ」
老人の家は公園に程近い古い団地の中にあった。さっぱりと片付けられた物の少ない部屋に案内されて待っていると老人がアルバムを何冊か持ってきた。丸いちゃぶ台の上に一冊を広げると、最初の頁におかっぱ頭の少女の写真があった。
「虫眼鏡のレンズを使つて自作した寫眞機で撮つた初めての寫眞です」
頁をめくると、亦同じ少女の肖像が現れた。髪型が三つ編みに変わり、制服らしいものを着ている。
「先の寫眞から一年後、また新しい寫眞機を作りました」
頁をめくる度に同じ少女が現れた。いや同じ少女だが、頁をめくる度に大人びてゆく。
「毎年寫眞機を作り彼女を寫すのが私の神聖な儀式となりました。さうして彼女も私の気持ちに応えて呉れました」
或る頁からはその女性のヌード写真が続いていた。一年に一枚づつ、一体何枚あるのか、私は一冊目を見終わると次のアルバムを手に取った。やはり同じ女性が艶然と裸体を曝していた。次第に年齢を重ねていく一人の人物が、単玉のレンズの静かな温かみのある描写で記録されている。こんなやりかたがあったのかと、私は写真を撮る者として悔しいような気持ちを抱きつつなおも頁をめくった。写真の女性は年齢を重ね、中年期にさしかかっている。気をつけてみると、女性の背景に写っている室内も、どの写真も同じようでいて、少しづつ変化しているのだ。物が増えたりなくなったり、最初の頃と比べると次第に生活感が写り込み、所帯じみた感じもしてくる。
私は無言で頁を繰り続けた。アッジェに作品を見せられたベレニス・アボットも、きっとこんな気持ちだったのだろうと私は思った。アルバムの女性は初老を迎えていた。変化してゆく肉体を温かい視線で写真は写し続けていた。何やら神々しいものを感じさせる写真であった。
かつて「ヘアヌード」が巷間に氾濫した時期に年増女優の写真集が売れたことがあって、おばさんの裸見て面白いのかと私は軽蔑の気持ちを抱いたものだが、今大いに反省をしている。それは記録され保存されるべき必然性があったのだ。某野球監督の妻の水着姿も、百歳の双子姉妹の写真集も、流行に追随した企画ものと受け取ると薄っぺらなものに感じられるが、それらの総てを通覧したとすれば、どんなに面白いものが隠されているかもしれない。もちろん年増女優や監督夫人が鑑賞に値する作品になっていたかどうかは別問題なのであるが。老人が私に見せてくれた作品は私に新たな写真の記録性と思考の広がりを示唆した。
「さうです、彼女は私の妻です……遠い昔です」
老人は私に言った。私はゆっくりとアルバムの頁をめくっていった。しかし、幸福そうな連続写真は突然に途切れ、そこから後は、写真の貼られていない白い頁が続いていた。
私は何やらいたたまれぬような気持ちになってアルバムを閉じた。老人は遠くを見るような目をして煙草を吸っていた。
「奥さんは……」
私は、何か云わなければと思いつつ言葉を探せなかった。
「只今。なんやお客さんですか」
襖を開けて顔を見せたのは誰あろう写真の中の人。彼女は私の持っているアルバムを見ると云った。
「あ、またそんなもん人さんにお見せして。ははははははは。すんまへんなあ。どうしようもないすけべおやじでっしゃろ。はははははは。尤も五年前に前立腺を手術しまして、それからはまあ大人しなりましたけれど。ははははははは、あれま、お茶もお出しせんと、ちょっとまっとくれやっしゃ。はははははは」
私は早々に辞去した。 老人は遠い目をしたままだった。
第3話 ほいとのはなし
もともと自動車の運転は好きではなかったのです。この軽自動車も、月に一度、近所のスーパーに買い物に行くのに使う程度で、二回目の車検が来ても走行距離は三千キロ程だったのです。通勤は電車だったし、生活に車はさほど必要ではなかったのです。
ところが不景気で収入が目減して生活を見直すことになり、車を処分しようということになりました。それなら、その前に一家で最初で最後のロングドライブに行こうと思いついたのです。とりあえずは日本海を見に行こうと、土曜日の朝早く家を出てのんびりと走り、午後遅くに海について、沈む夕日を眺めました。
…このまま帰るのはもったいない様な気がするなあ…
私が言うと、息子は大喜びしました。妻もまんざらではなさそうでした。その晩私たちは生まれて初めて車の中で一夜を明かしました。
そして、それ以来、私たちは家に帰っていないのです。
あれから何年経ったのか、もうよく判らなくなってしまいました。海岸に沿って日本列島を何周もしている筈です。目的地もないので、ここが何処なのか、明日何処へ行くのか、私たちには判りません。最初のうちは、時々銀行をみつけて貯金を下ろしたりしていましたが、それもいつしか底をついてしまいました。
…お金がなくては、この夢みたいな暮らしもおしまいかな…
しかし、この際ものは試しだと思って、私は道端に車を寄せて停まり、パワーウインドウを下ろすと、傍を通りかかった人にいってみたのです。
…哀れな乞食にお恵みを…
私は、子供の頃祖母がいっていた『ほいと』ということばを思い出しました。どこか薄汚れたお遍路さんや行者のような風体で門口に立っていた物乞いを祖母は、
…あれはほいとじゃ…
侮蔑をこめて言いました。しかしおばあさんは必ず米や小銭を彼らの頭陀袋や鉢に入れてやりました。
私が風呂に入るのを嫌がると、
…そんな汚いなりではほいとの子のようじゃ…
と言っていたおばあさん。
おばあさん、私は、あなたの孫は本当にほいとになってしまいました。
門口に自動車で乗りつけるふざけたほいとではありますが、それでも行く先々で一家三人が食うに困らずガソリンもなんとか入れるだけのお恵みが不思議にいただけるのです。
物乞いを始めてから暫くして、車のナンバープレートが無くなっているのに気がつきました。私の運転免許証も、何処へ置いたのか判らなくなってしまいました。妻のクレジットカードや銀行のキャッシュカードも見当たりません。それに車検証も見つからないのです。もしも検問に引っかかったら一巻の終わりですが、不思議なことに今まで一度も警官に呼び止められたことがありません。一斉検問があって、列に並ぼうとしても、係の警官は私の方を見て、あっちへ行けと手を振るのです。
一体これはどういう事なのでしょうか。私たち一家はどうなってしまったのでしょうか。
走り続けているときは何も考えていないのですが、時々道端に車を停めている時など、考えてしまうことがあります。ほいとになるということはどういうことなのでしょう。私たちは本当にここに存在しているのでしょうか。いると思っているのは私たちだけで、実は私たちはもうこの世にはいないのではないか。そんなふうに考えて背筋に冷たいものが走ることがあります。しかし、私たちが見えているからこそ人々は私たちにお恵みを下さるのだし、見えていればこそ警官はあっちへいけと手を振るのです。でも何故こっちへ来いではなくてあっちへいけなのでしょう。
一度、かつて私たちが暮らしていた町へ、住んでいた家へいってみようと思ったことがありました。でもどうしても行くことができませんでした。道がよく判らないのです。道路標識を見てもと居た町の名前の方へ曲がるのですが、気がつくとそこを通り過ぎているのです。引き返してみても同じです。見覚えのある景色のような気がするし、全く知らない場所のような気もするし、夢の中でもがいているような感じなのでした。
私たちは居場所を無くしてしまったのでしょう。なにやら寂しいような気もしますが、「寂しい」という感情が一体どんなものであったのか、今ではそれすら判然としない私たちなのです。只ただ走り続けて日を送る、そしておそらく、今は覚えている過去の総てを忘却してしまうのだろうと私は思うのです。
私たちはそんな風に生きているのです。聞いてくださって有難うございます。憶えてくださっても忘れてくださってもかまいません。私たちは直ぐにあなたのことを忘れてしまうとおもいますが……
それでは、ご免くださいませ。
第2話 獺祭老人伝
谷神不死 是謂玄牝
玄牝之門 是謂天地之根
緜緜若存 用之不勤 (老子)
おばあさんが亡くなってしばらくして、おじいさんは
「わしは隠居するけんの」
といって、裏の蜜柑山のてっぺんに小屋を建ててそこにひきこもり、食事の時以外は家に帰ってこなくなった。
「おじいの好きにさしたらええ」
といっていたぼくの父も、ちょっと心配になりのぞきに行ってみると、小屋中に、とてもたくさんのエロ本があふれていた。
「これはどうしたんぞ」
あきれた父がときくと、
「自転車で松山まで買いに行ったのよ。毎日いくので本屋もびっくりしとる」
おじいさんは上目使いに父を見ていたずらっ子みたいにいった。
「自転車で行っては時間もかかるし、しんどかろう」
母が心配すると、
「飛ばすけん、すぐよ。こないだ警察のまえを走ったらパトカーが追いかけてきての、自転車でそんなに飛ばしたらいけんゆうておこられたわい」
いかにも面白そうに笑うのだった。
まあ年寄りのすることだからということで、おじいさんはそれからもエロ本集めに精を出したが、
「子供は行ったらいかん」
と僕は小屋に出入り禁止にされてしまった。 それでも時どき小屋を訪ねると、おじいさんは喜んで中に入れてくれ、僕は喜んで漫画や写真から世界の秘密を学んだ。といっても、そのころのエロ本は今と比べると慎みぶかくて、いたるところに黒い墨ベタが印刷されていて、秘密の探求を拒むのだった。
「なんで見えんようになっとるんじゃろ」
あるとき本のページを繰りながらぼくが言うとおじいさんは
「大秘密がそこに隠されとるのよ、この世のすべてのものはそこからでてきたんぞ」
じっとぼくをのぞきこむようにしてそういった。
それから何年かしておじいさんは死んだ。死ぬ前の日、母屋で昼飯を食べた後、母に
「あした死ぬるけん、皆にゆうといてくれ」
といって小屋に帰ってその晩は食事にこなかった。心配した父が小屋を訪ねるとおじいさんは別段変わったところもなく、酒をちびちび飲みながらエロ本をながめていた。
翌朝食事に降りてこなかったので、母が行ってみるとおじいさんは肘枕してうたた寝するうような格好で死んでいた。
集まった親戚の男連中は、形見分けと称してエロ本を嬉しそうに物色して持ち帰った。実際、おじいさんの財産はそれ以外にほとんど残されていなかったようだ。ぼくも大人たちのすきをみて何冊かシャツの中にたくし込んだ。
「あんなに好きだったのだから」
と、お棺の中にもたくさんのエロ本が詰め込まれた。火葬場の煙突から煙といっしょに、ヌードグラビアの焼け残りが大量に空に舞い上がり、辺りに降って皆をあわてさせたが、翌日骨を拾いに行って皆はもっとあわてることになった。
缶の蓋をあけてみるとお骨がなかったのだ。焼け残りのエロ本とお棺の残骸はあるのに、おじいさんの骨は喉仏ひとつものこっていなかった。大騒ぎになりかけたが。おじいさんの妹である広島のおばあちゃんが
「ほんに兄さんらしい最後じゃなあ」
といって骨壷にエロ本の灰をすくって、その場をおさめた。
形見分けしたといっても大量のエロ本が残されたままになっていた蜜柑山の小屋は、僕の聖域となっていたが、ある年の台風でエロ本もろともどこかへ吹き飛ばされてしまった。
第1話 裸で暮らした我等の先祖は
起きぬけにテレビをつけたら女性アナウンサが裸でニユウスを読んでゐたので、自分は彼女が何を云つてゐるのか理解できなかつた。これは何のハプニングだらうと思つてゐたが、なんの混乱もなく彼女は平然とニユウスを読み終へて、つづいて登場した気象予報士の男もやはり裸で気圧配置を全身を使つて説明するものだから自分は無修正の画面を呆然と眺めてゐたところへ、小学生の娘が起きてきて、「おはよう」とも云はず暫くテレビを眺めてゐたが、娘はやおらパジャマも下着も脱ぎ捨てて台所へ行つてしまつたので、娘に続いて寝室から出てきた妻は裸の娘に小言を云ひかけて、テレビを見たまま暫く動かなくなつた。
テレビでは別のアナウンサがやはり裸でニユウスを読んでゐたのだが、妻は何やら納得したやうな表情になるとやはり着ているものを脱ぎ捨てて朝食の支度をしに行つてしまつた。
テレビニユウスは終はりに近づき「では中継画面を見ながらお別れです」と、通勤者が増え始めた駅前の風景を映し出したが、そこに映つている人々も皆裸だったので自分は何やら得体の知れぬ恐怖を覚えたのだが、妻と娘は平然と裸で朝食を食べて真つ裸に鞄やランドセルをつけて、玄関で靴を履くべきかどうか一瞬悩んで、しかし裸足で元気良く出かけて行つた。
自分はベランダへ出て二人の後姿や、同じ団地の住人たちが、やはり裸で出掛けて行くのを暫くながめてゐた。
その日から自分はひきこもつてしまつた。
寒い冬になつたら皆だうするのだらうと思つてゐたのだが、雪の日も人々は平気で丸裸で過ごしていた。人類は新しい段階に到達したのかもしれぬと思つた。しかし、自分は誰とも口をきかず家の中で過ごした。時々妻は溜息をついたが、服を脱げとも、何故脱がないのかとも云はなかつた。自分も妻に何故服を脱いだのか聞かなかつた。
時折自分はテレビを見た。総理大臣も国会議員も浮浪者も裸だつた。外国人もみな裸だつた。旅番組では、レポオタアが、裸で買い物や食事をしているくせに、温泉に入るときには何故か胸元までバスタオルをしつかり巻いて湯船に浸かつているのが不思議だつた。
一年が過ぎた。ある夜、自分が眠つていると娘が妻に「お父さんは何時になつたら会社へ行くのだらう」と云つているのが聞こえた。自分は深夜眠れぬままに自転車に乗つて国道沿いを町外れまで行くと道端に何台ものエロ本の自動販売機があつたので一冊買つてみると出てきた本の表紙は服を着た女性の写真だったが頁をめくると、中身は裸の、何のことはない普通のエロ本だつた。自分は急に腹が立つて、糞、金をかえせと自動販売機を蹴つたので防犯ベルがけたたましく響き渡つた。自転車に飛び乗つてその場を離れた自分は、少し離れた公園まで逃げてくると自転車を放り出し地面に寝転んだ。動悸がおさまると自分はなにかふつきれたやうな爽快な心持ちがして、着てゐるものを脱ぎ捨ててしまつた。それからポケツトに残つてゐた小銭を握りしめて自転車に乗つて帰つた。裸で自転車に乗るのは妙な気持ちだつたが、嫌ではなかつた。なんで自分は今までこんなにも頑なだつたのだらうと可笑しかつた。もう夜明けだつた。団地のごみステエションを見て今日が燃える粗大ごみの日だと知つた自分は帰宅するなり家中の服をゴミ袋に入れて収集場所に持つて行つた。快い疲労を覚えて布団に横になり、一眠りしたら髭を剃つて職安へ行かうと思ひながら目を閉じた。
で、 起きぬけにテレビをつけたら女性アナウンサが服を着てニユウスを読んでいたが自分は彼女が何をいつているのか理解できなかつた。頭の中にゴミ収集車のオルゴオルの音が響き渡つていた。